最近の親は子供の上手な叱り方を知らないといわれています。
下手に叱ると、子供が傷つくかもしれないと考えて、子供の言い分を聞く親もいらっしゃいます。
あるいは逆に、口うるさく叱って、むしろ子どもの反発を買って、小学生のうちから、子供が親の言うことを聞かなくなることもあるそうです。
いずれも原因ははっきりしています。
親の叱り方が下手だからです。
今回はそんな子供への叱り方がわからないという方に「子供の上手な叱り方」と「やってはいけないダメな叱り方」をご紹介します。
いやぁ。子供の叱り方って本当に難しいですよね。。。うちにも8歳になる娘がいますが、、うーん。「こういうべきかな?ここな黙ってみて見ぬふりすべきかな?」と本当に悩みます。
この記事ではそんな悩みを解決していきますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
目次
子供のダメな叱り方5選
そもそも叱らない
世の中には、ほとんど子供を叱らない親が存在します。
レストランで子供が駆け回って騒いでいても叱らない。
子供たちが周囲のみんなに迷惑をかけ、周囲のみんなが子どもたちを殴りたい気持ちでいるのに、当の親はニコニコ笑いながら「そんなことしちゃダメだよ」などと優しい声で注意するだけ。
子供がいたずらしても叱らない。子どもが宿題を怠けていても叱らない。
そんな親は「子供はのびのび育てたい」「学校という体制の中に押し込めたくない」などの言葉が口癖です。
このような子供を叱れない親の有様は決していいものではありません。
子供はきちんと叱り教育する必要があります。
他人のせいにした叱り方をする
最もダメ叱り方、それは「あのおじさんが怒っているからやめようね」「決まりなんだから、そんなことしてはいけないよ」という叱り方です。
もちろん図書館で子供が騒いでいるときに、そこの担当者がそれを言うのは当たり前です。
「ご迷惑と感じられる人がいるのでやめてください」
「決まりですのでどうかご理解ください」
こんな注意の仕方でいいと思います。
しかし、親の場合には、他人のせいにしたような叱り方では、子供は納得しません。
それに子供が「決まりがなければ何をしてもよい」「見つからなければ何をしてもよい」「文句を言われなければ何をしてもよい」と考えてしまいます。
それではきちんと子供に価値観を教えていることにはなりません。
叱るべきときは、しっかりと、なぜ悪いのかをわからせる必要があります。
それこそが叱るということです。
叱りすぎる
叱れないのも問題ですが、また逆に叱りすぎることもダメな叱り方です。
そもそも、叱りすぎると叱ることの効果がなくなってしまいます。
叱っているうちに、次から次へと思い出して「あれもこれもダメだ。あのときこうした。もっと前もこうだった」というように、あれこれ叱りだす親もいます。
最初は宿題を忘れたということだったのに、部屋が汚い、寝坊する、時間を守らない、親の手伝いをしないなどということを言い出し、最後には、食事をするときに「おいしい」と言わないことまで怒り出す人もいます。
そして叱っている本人も、何を叱っているのかわからなくなって終わることさえあります。
もちろん、そのような叱り方をされて子供の行動が改善されるはずはありません。
ほかの人と比べる叱り方も、子供を傷つけるだけで効果はありません。
「A君はいつだって100点なのに、あなたは何よ」
「お兄ちゃんはあなたの歳では、いつも100点だったのよ」
こんなことはたとえ、頭の中では考えたとしても口にだすべきではありません。
親は励ましのつもりで言ってるのかもしれませんが、まったく励ましにはなっていません。
人格を全否定する
そして最も悪いダメな叱り方は、感情に任せて子供の全人格すべてを否定することです。
「あんたはなんて情けない子なの」
「あんたのような子どもはいらない」
「あんたみたいな子を持って恥ずかしい」
「我が家の恥だ」
親はその場限りの感情に任せていっているのかもしれませんが、子供の心にはトラウマとして残りかねません。
感情的に叱る
また感情的に叱る人は、子供が改善したらしたで、また叱る傾向があります。
たとえば「たまにはお手伝いしなさいよ」と親が怒るので、子どもはお風呂掃除を手伝う。
すると「こんな掃除の仕方をして!これじゃ意味がないでしょ!」と叱って、やり直しをさせる。
その後も「まだ浴槽が汚れている!こんなこともできないんだったら勉強でもしてなさい」とまた叱る。
そして最後には「何もやらせてもだめなんだから」と捨て台詞を残すのです。
これでは、子供をいじめているとしか言いようがありません。
子供の上手な叱り方7選
叱り方にはテクニックがあります。
次は子供の上手な叱り方を具体的に7つご紹介します。
自尊心を保つ
最初の子供の上手な叱り方はこれです。
叱るときの最大のコツ、それはあくまで自尊心を保つということ。
中学生ぐらいになれば、ぐうの音もでないくらいに自尊心を打ち砕いて、心の底から反省させる方法もあります。
しかし小学生までの子供にそのような叱り方をすると、自己万能感を持つことができなくなります。
自己万能感とは「自分には特別な能力がある。努力すれば必ず世界一になれる」と、自分のことを肯定できる力のことです。
人間は、自分には人並み以上に能力があるという思いがないと、堂々と生きていくことができません。
人並み以下だという意識を持っていると自分に自信が持てなくなります。
そういう意味でも、小学生以下の子供に対しては、自尊心を打ち砕かない程度に叱る事が何よりも上手な叱り方となります。
子供の叱り方としては、人格や能力を全否定するのではなく、あくまでひとつの行動、一連の行動について叱るようにします。
「あなたの全体が悪い」のではなく「あなたのした今度の行為は悪い」という叱り方です。
具体的には次のような叱り方が効果的です。
「本当は力があるのにお前らしくない」
「お前は十分な力を出し切っていない、こんなはずではないだろう」
このように叱ることによって、潜在能力を認めた上で叱ることができます。
もし感情的になって、つい全否定めいたことを言ってしまったら、後で必ず「本当はお前には力がある」などとフォローするようにしましょう。
ひとつのことに絞る
次の子供の上手な叱り方はこれです。
ひとつのことに絞って叱る。
子供を叱るとき、いくつものことを言うのではなく、ひとつに絞って叱るようにしましょう。
叱っているうちに子供の欠点をいくつも思いだしたとしても、そして子供のだらしない行動のすべてに関連性があるにしても、ひとつを取り出して厳しく叱らなければいけません。
そうすれば、時間も短くすみ、焦点が絞れて、何に特に注意すればよいかが子供自身にも分かりやすくなります。
叱るときは30秒以内で
上手な叱り方として、叱る時間を意識することも大切です。
長々と叱る親がいます。次々と以前の子供の行為を思いだし、一つ一つ説教する。
子供が泣き出すまで叱りつけないと我慢できない親もいます。
子供が泣き出せば許すといった親も少なくありません。
子供に反省の弁を言わせないと気がすまない親もいます。
しかし、それは時間と労力の無駄です。同時に子供の反発を招くだけです。
叱るというのは、子供を泣かせるための行為ではありません。しつこく叱って、子供にうるさがられる行為でもありません。
あくまで、自分がした行為が悪かったと思わせるための行為です。
だったら時間は長くかける必要はありません。
30秒ほどでガツンと言うのが上手な叱り方です。
そして叱っている理由をちゃんと説明する。
それには30秒も必要ないはずです。
できるだけ理屈を説明する
頭ごなしに叱る人がいます。
「そんなこと決まっているでしょう」「なに、ばかなことしているの」と怒鳴りつける。
子供が反論しようとすると「屁理屈をいうんじゃない!」といってまた叱る。
しかし、これは好ましい叱り方ではありません。
このような決めつけた話し方すると、子供に論理性や発信力が備わりません。
そもそも子供は自分の言いたいこを言えず、不満に思うでしょう。
多くの場合、子供にも何らかの理由があって行動をしています。
「そんなことをしても意味がないんじゃないか」
「そんなことはしたくない」
こう思っているから子供たちもするべきをしないのです。
子供は自分の気持ちを言葉でうまく表現することがまだまだできません。
だからもぞもぞ話したり、あるいは泣いて表現するのです。
頭ごなしに怒鳴りつけるのではなく、子供の言い分を聞き、それがいかに間違っているのかを説明するのが上手な叱り方です。
「なぜ、そんなことをしたのか言ってごらん」
「どうして、それが悪いことなのか、言ってごらん」
「宿題をサボったのはなぜ?言ってごらん」
脅迫的に言うのではなく素直に言わせる。きちんと自分の意見をまとめさせる練習と思えばいいでしょう。
その上で、子供にきちんとわからせるのが、上手な叱り方です。
「確かに、しかし、」のパターンを使う
子供の上手な叱り方として「確かに、しかし」のパターンで叱ることをおススメします。
ひとつは「確かに」の後にほめておいて、「しかし」の後で叱る方法です。
具体的にはこのような感じです。
「確かに、これまではお前はよい子だった。感心することも多かった。しかし、今度はいったいどういうことなのか」
もう一つの方法は、逆に「確かに」の後にけなしておいて、「しかし」の後でほめる方法です。
「確かに今回はこんなにひどい。しかし本当は、お前はもっとできるはずだ」
もちろん「確かに、しかし、」という言葉を文字通り使う必要はありません。
「という面はある。だけど」など、言い方は自分なりにアレンジすればいいでしょう。
具体的に目標を与える
子供が言うことを聞かないとき、勉強しないとき、何かをサボるときというのは、どうしてよいかわからなかった場合が多いのです。
どこをどのように勉強していいかわからない。何をすればいいのかわからない。
だから何もしない。
このようなパターンが多いのです。
したがって、こんなときに抽象的に「もっと勉強しなさい」と叱ってもあまり効果はありません。
勉強に関して言えば「なぜ、ワークブックを〇〇ページまでやらなかったの?」というように叱ります。
そして「明日までに〇〇ページまでやりなさい」というように具体的に指示します。
このような具体的な指示があってこそ、子供はやる気を起こすんです。しかもそのほうが、きちんと勉強したかが一目瞭然になって、わかりやすい。
褒美を与えるのも悪くない
「テストで100点を取ったらゲームを買ってあげる」というように、成果について褒美を与えることについては、賛否両論があります。
これはあくまで僕の考えですが、褒美を与えてやる気をうながすことは決して悪いことではないと思っています。
人間、何らかの成果を求めて行動する。
純粋に勉強が好きで勉強することなどまれなケースです。
大人が仕事をするのも、それと引き換えに報酬があったり、出世があったり、周囲の評価があったりするからです。
それと同じように、目の前にわかりやすい目標があることは、努力したい気持ちをだすための大事な要素です。
なので叱った後に「今回はよくなかったけど、次回しっかりやったら、ご褒美に~をあげる」というようにする。
そうすれば、かなりきつく叱っても、子供は納得します。
ただし褒美はあまりにも高価なものであったり、あまりに褒美をあげすぎるのは問題があると思います。
月に一度くらい、子供が普通にほしがるようなものを、成果を上げた褒美という形をとって与えるぐらいがいいんじゃないでしょうか。
恥ずかしい人間にならないためにも
子供の上手な叱り方とダメな叱り方をご紹介しましたがいかがでしたか。
最後にご紹介した内容をもう一度まとめておきます。
ダメな叱り方は
- そもそも叱らない
- 他人のせいにした叱り方をする
- 叱りすぎる
- 人格を全否定する
- 感情的に叱る
上手な叱り方は
- 自尊心を保つ
- ひとつのことに絞る
- 叱る時間は30秒以内で
- できるだけ理屈を説明する
- 「確かに、しかし、」のパターンを使う
- 具体的な目標を与える
- 褒美を与えてみる
言うまでもありませんが、子供は自分ですべてを判断できるわけではありません。
わがままを言うことだってあります。
屁理屈を言うことだってあるでしょう。
他人の迷惑を少しも考えていないこともあります。
そのような場合、いかにその行為が間違いであるかを教える必要があります。
叱るという行為は、そもそも親がしっかりとした価値観や考え方をもっていないとできないことです。
そういう意味では、親自身も子供とともに日々成長していかなければいけません。
叱ることは難しく大変なことですが、子供にしっかりとした価値観を植え付け、社会に出て恥ずかしくない行動のできる人間に育てることはとても大切なことです。
今回ご紹介した「子供の上手な叱り方」ぜひ参考にしてくださいね。
次は子供の上手な褒め方6選!何より「自己万能感」を植え付けよ!です。ぜひ、合わせて読んでください!
※関連記事
子供の自主性や主体性を育てる5つの具体的な方法とは?ダメな親の特徴もご紹介します!









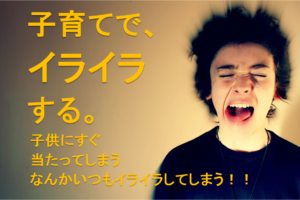






コメントを残す